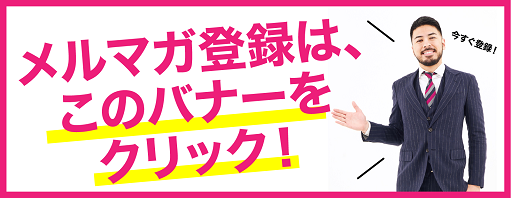IT部門に求められる事業継続計画(BCP)
- 2022年3月29日
- 中小機構 中小企業支援アドバイザー 眞本崇之
- 事業継続計画
- BCP

事業継続計画(BCP)をご存じでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の影響や自然災害などに被災するような、近年多発している緊急事態の場合でも、事業を継続するために会社としてどのような手段を取るべきかを計画しておくものです。
今回の記事では、「事業継続計画(BCP)」のうち、特に実現に向けた重要な位置づけを占めるIT分野についてまとめてみました。
事業継続計画(BCP)とは
自然災害や事故は、いつ発生するか予想がつかず、予期せぬ被害が発生する可能性があります。そこで、企業が緊急事態時の被害を最小限に抑え、事業が継続できるように対策や早期復旧の方法をまとめたものが事業継続計画です。「Business Continuity Plan」の頭文字を取ってBCPと略されて言われています。
事業継続計画(BCP)は、2011年の東日本大震災で多くの企業が被災したことで注目され始め、昨今の豪雨による自然災害や、新型コロナウイルスの流行など、企業はあらゆる緊急事態を想定し、緊急時に事業の継続・早期復旧を図ることが重要となります。
中小企業庁の中小企業BCP策定運用指針によると、BCPの策定において、(1)優先して継続・復旧すべき中核事業を特定する、(2)緊急時における中核事業の目標復旧時間を定めておく、(3)緊急時に提供できるサービスのレベルについて顧客と予め協議しておく、(4)事業拠点や生産設備、仕入品調達等の代替策を用意しておく、(5)全ての従業員と事業継続についてコニュニケーションを図っておくことが必要となります。
また、似たキーワードで『事業継続力強化計画』があります。
事業継続力強化計画は「簡易版BCP」と言われていて、事業継続計画(BCP)も事業継続力強化計画も、自然災害等による緊急事態時の対策を計画する目的には大差はありません。
事業継続力強化計画は、中小企業強靱化法によって定められた認定制度です。認定を受けることで補助金審査での加点措置、税制措置、日本政策金融公庫からの金融支援を受けられるメリットがあります。
事業継続計画(BCP)に欠かせないIT関連の取り組み
ここから、事業継続計画(BCP)の中で取り上げられるIT関連の取り組みについて紹介していきます。
昨今、ほとんどの企業で、ホームページ・予約システムといった顧客向けのITツールや、倉庫管理・在庫管理・会計といった社内における管理システム、社内コミュニケーションツールに至るまで、多様なITを活用した経営を行っています。そのため、使用しているIT環境が停止してしまうと、企業経営に大きな損害が出てしまうことが考えられます。
事業継続計画(BCP)では、緊急時にITシステムの運用を維持できるか、また、安否確認など社内連絡網としてのITツールの活用も緊急時を想定して検討・準備しておく必要があります。
いくつか例を挙げて説明をします。
〇データバックアップの準備
パソコン本体のハードディスクに保管されたデータは、そのパソコン自体が水没や火災などにより使えなくなった場合に、データを取り出すことが難しくなります。
そこで、有効な手段がバックアップです。遠隔地のデータセンターまたはクラウドサービス上に、データのバックアップを置いておくことが推奨されています。
一般的に、クラウドサービスのサーバやデータセンターは地震災害が少ない地域に置かれることが多いことに加えて、データセンターの建物や設備に水害や火災の対策が施されているため、自社で管理するよりも安全にデータを守ることが可能となります。仮に会社が被災をした場合でも、遠方にあるデータは守られるため、データを消失するリスクが分散されます。
ここからアプリ/関連アプリ:ここからアプリ「オンラインストレージ」アプリ検索結果
〇テレワークの準備
テレワークとは、「tele=離れた場所」、「work=働く」という意味の単語を合わせた造語です。
昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、テレワークが急速に普及しています。
会社以外の場所からでも社内ネットワークにアクセスする、またはクラウドサービスを利用するなどにより、会社に行くことができなくても社外から業務を行うことができるようになります。
テレワークで全ての業務を行うことができないとしても、事業遂行に最低限必要な業務を行える状態にあれば、事業を継続できないというリスクを最小限に抑えられます。
テレワーク環境の整備や、テレワーク活用による勤務を日頃から実施することは、事業継続計画(BCP)における有効な手段の1つに挙げられます。
ここからアプリ/関連特集記事:テレワーク特集
ここからアプリ/関連特集記事:アフターコロナを見据えたテレワーク(5)テレワーク導入に役立つ知識の紹介(特集編)
〇安否確認や連絡体制の準備
災害時には、電話やメールといった普段使っている連絡ツールが利用できなくなることが想定されます。実際に、東日本大震災の発生時には電話やメールが不通になり、SNSが連絡手段として活用されました。
近年、ビジネスチャットやSNSをコミュニケーションツールとして活用する企業が増えています。災害時に従業員の安否確認をスムーズに行える掲示板や安否確認サービスのような災害発生時に特化したサービスもあります。
事業継続計画(BCP)では、災害時に従業員の安全をどのように確保するのか、そして、安否確認などの連絡体制をどのように行うか、代替手段を含めて検討することが必要です。
災害対策にITを活用した事例
ここでは、テレワーク導入を促進させ、災害対策を計画・実施した事例記事を紹介します。
BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう!/取組事例:テレワークの導入が自社PRにも貢献(株式会社シンク・タンクの取組事例)
株式会社シンク・タンク(内装施工業・広島県)では、二度の西日本豪雨を経験したことから、自社の事業継続力強化計画を策定しました。
ITに関連する災害対策事項として、主にデータ保存にクラウドサービスを活用すること、業務の一部をテレワークで対応できるように計画しました。
実際に、新型コロナウイルス感染症の拡大期においては、テレワークを活用したことで利便性と安全性が担保されました。
事業継続計画(BCP)策定のすすめ
災害などにより、電力・水道などの停止、電話などの連絡手段や情報通信ネットワークの停止、IT機器の故障やデータ消失、交通機関の乱れなど、緊急事態は様々な被害が想定されます。
こうした緊急時への対応は、IT活用に止まりません。
例えば、自家発電などのインフラ整備、耐震・防火設備などの刷新、企業間や地域での連携による協力体制の強化、災害保険への加入、災害時必要物資の確保、防災マニュアルの作成や従業員教育・防災訓練の実施など、様々な観点で取り組むことが求められます。
事業継続計画(BCP)にはテンプレートが存在しません。他社のBCP対策を自社に当てはめてもうまく機能しない場合があります。
下記のサイトに掲載されている計画策定のポイントや、その他事例などを参考に、緊急事態時の対策や早期復旧の方法をまとめてみましょう。
参考
・中小企業庁/中小企業BCP策定運用指針
・J-Net21/備えあれば憂いなし、BCPのススメ
・中小企業強靭化支援ポータルサイト/BCPはじめの一歩 事業継続力強化計画をつくろう!